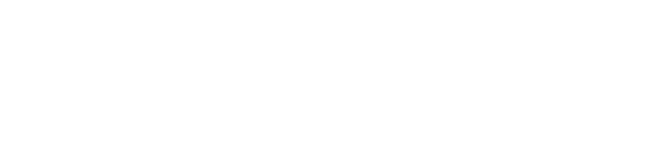競馬には専門的な言葉や表現がいくつもありますが、「脚質」もそのような言葉のひとつではないでしょうか。
馬は「両脚」で走る動物なので、その「脚」の能力を表しているような言葉な気もしますが、実際にはどのような意味をもっているのでしょう。
本記事では、競馬の「脚質」について解説します。
併せて、脚質ごとの勝率やメリット・デメリットなども紹介するので、脚質について知りたい方はぜひ参考にしてください。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/
競馬の脚質とは
競馬の脚質とは、「競走馬が得意とする走り方」を指します。
我々がマラソンのようなレースを走るケースを考えてみると、先頭集団で他のランナーを引っ張るような形で走る人もいれば、前半は力を溜めて後半でスパートするような形で走る人もいるでしょう。
競走馬に関しても同じことが当てはまり、集団の前のほうで走るのが得意な馬もいれば、他の馬を後ろから見るような形でレースを進めて、最後の直線で残っている力を爆発させるような馬もいます。
競走馬がどのような位置でレースを進めるかはそれぞれの馬の脚質でおおよそ決まるので、馬券を購入する方はレースに出走する馬の脚質を把握しておくのがおすすめです。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/
競馬の脚質一覧

競馬の脚質は大きく、「逃げ」「先行」「差し」「追い込み」「まくり」に分類できます。
それぞれの脚質の特徴を、以下で詳しく解説しましょう。
逃げ
「逃げ」は名前のイメージどおり、レースにおいて先頭を走る脚質を指します。
どのような形で逃げるかは馬によって異なり、後ろを引き付けるような形で逃げる馬もいれば、大逃げといって着差を大きく付けるような形で逃げるパターンもあります。
また、スタートの出が悪いと逃げようと思っていたのに逃げられないこともありますし、逆にスタートがよすぎて自然と逃げの形になってしまうこともあるでしょう。
一般的にレースのペースは、逃げ馬がどれくらいのペースで逃げるかによるため、レースの流れを左右する脚質といえます。
また、ファンの心に深く刻まれるレースをすることが多いのも、「逃げ」という脚質の大きな特徴です。
古くはサイレンススズカやセイウンスカイなどの名前が挙がりますし、最近では名手武豊を背に宝塚記念を逃げ切って勝利したメイショウタバルも逃げ馬の一頭です。
先行
先行は、馬群の前のほうでレースを進める脚質の馬を指します。
レース中に「ここより先が前、ここより後ろが後」といった表示が出るわけではないので、「どのあたりを走っていれば先行か」に関して厳密な決まりがあるわけではありません。
そのため、「馬群の前のほう5%~40%あたり」を駆けている馬を、「先行」ととらえるのが一般的です。
18頭立てのレースであれば、馬群の形にもよりますが、「おおよそ3番手~8番手あたりまでが先行」という認識で問題ないでしょう。
代表例としては、天皇賞春の連覇を達成するなどG1を4勝したメジロマックイーンや、引退レースとなる有馬記念を1年ぶりの出走で勝利したトウカイテイオーなどが挙げられます。
差し
「差し」は、レースにおいて馬群の後ろのほうを走る脚質を指します。
分類上、先行馬の後ろを走るのが差しの馬という扱いになりますが、「ここからここまでが先行馬」「ここからここまでが差し馬」と明確に分けられるわけではありません。
逃げと追い込みを除いた馬群があったとき、道中のポジションの動きによって先行と差しが入れ替わることも多々あるからです。
差しの馬は序盤は脚を温存しているため、その真価は最終直線で発揮され、前の馬を一頭また一頭と追い抜いていく様は圧巻です。
代表例としては、64年ぶりに牝馬としたダービーを勝利した名牝ウオッカや、史上初めて無敗での三冠達成を成し遂げ、その強さから「皇帝」と呼ばれたシンボリルドルフなどが挙げられます。
追い込み
「追い込み」は、「逃げ」と対局の存在であり、馬群の最後方を走る脚質です。
レースに出走する頭数にもよりますが、馬群から離れて後方で走っている馬が2,3頭いるとしたら、それらの馬が「追い込み馬」だと考えておいて問題ありません。
差しの馬より後方にいることから、ほぼすべての力を最終直線まで温存して、最終直線ですべての馬を抜き去るような豪快なレースが特徴です。
追い込み馬が推し馬なら、最終直線での応援に熱が入ること間違いありません。
代表例としては、皐月賞とダービーを勝利し、種牡馬としても多くの活躍馬を輩出したドゥラメンテや、「積んでいるエンジンが違う」とも称された末脚でG1を6勝したグランアレグリアなどが挙げられます。
まくり
まくりは、レース前半は馬群の最後方付近に位置しつつ、3~4コーナーで徐々にポジションを押し上げて先団に並んでいき、その勢いのまま先頭でゴールを狙うような脚質です。
レース序盤は馬群の後方にいることから途中までは「追い込み」と同じようなポジション取りになります。
ただし、追い込み馬が最終直線まで脚を温存し続けるのに対して、まくり馬は馬群の外を押し上げるような形で動いていくのが、追い込みとまくりの違いです。
まくり馬に騎乗しているからといって、必ずしもすべてのレースでまくりを打てるとは限らないので、好走の可能性がジョッキーに大きく依存する脚質です。
まくり脚質の馬が動くと自然とレース全体も動くため、レースのペースや競走馬の体力に大きな影響を与える脚質ともいえるでしょう。
競馬の脚質ごとの勝率
競馬の脚質にはそれぞれ特徴がありますが、馬券を購入する立場として気になるのは、「レースで有利なのはどの脚質?」ということではないでしょうか。
レースの距離や実施されるコースなどによって脚質の有利・不利は変わってくるため、一概にどの脚質が強い(or弱い)ということはできません。
ただ、すべてのレースをひっくるめて脚質ごとの勝率を算出することは可能です。
直近2年間での脚質ごとの勝率を、以下に表でまとめました。
なお、馬によってはレースでの通過順がバラバラで単一の脚質に定義できないこともあるため、勝率の合計が100%に足りない点には、ご留意ください。
| 脚質 | 勝率 |
| 逃げ | 27.1% |
| 先行 | 22.5% |
| 差し | 19.6% |
| 追い込み | 9.7% |
| まくり | 18.9% |
現代競馬ではレース中になるべく前のほうのポジションを確保しておくのが望ましいといわれていますが、各脚質の勝率からも、それが裏付けられる結果となりました。

競馬の脚質はどこで見る?【見方・調べ方・決め方】

脚質は、それぞれの競走馬の馬柱を見ることでおおよそ確認できます。
たとえば、ピューロマジックという馬が2025年のスプリンターズSに出走したときの3走前、4走前の馬柱は以下のとおりです。

ピューロマジックという馬は、シルクロードSでも昨年のスプリンターズSでも、「3コーナーと4コーナーの通過順がどちらも1番手」ということがわかります。
そのため、本馬は逃げ馬であり、今回のレースでも逃げの手に出てくるであろう可能性が高いことがわかります。
同様に、同じレースに出走していたドロップオブライトという馬の前走、前々走の馬柱は以下のとおりです。
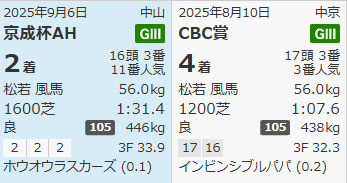
ドロップオブライトは、前走の京成杯AHでは終始前から2番手で走っているので、逃げや先行の形でレースを進めていることがわかります。
しかし、前々走のCBC賞では17番手や16番手と、かなり後方でレースを進めています。
そのため、本馬は特定の脚質に当てはめたレースをするのではなく、レースの流れやほかの馬の動向を見ながら自在に走る馬であろうと想像できるでしょう。
馬柱は競馬新聞やJRAのサイトなどで確認できるので、レースにおいてどの馬がどのような脚質でレースを進めるかを判断するための材料として、確認するのがおすすめです。

競馬の脚質ごとのメリット・デメリット
競走馬はさまざまな脚質でレースを走りますが、メリット・デメリットはそれぞれの脚質で異なります。
ここでは、競馬の脚質ごとのメリット・デメリットを見ていきましょう。
逃げのメリット・デメリット
逃げのメリットは、自分でレースのペースを作りやすいことです。
自分に有利なペースで逃げてラップを刻み、余力を残して最終局面を迎えることができれば、そのまま逃げ切って勝利しやすくなります。
また、ほかの馬にぶつかったり進路をふさがれたりといった不利を受けにくいのも、逃げのメリットのひとつです。
反対に、逃げのデメリットとしてはターゲットにされやすいことが挙げられます。
後ろの馬は、逃げ馬を最後に交わせるようにレースを進めればよいわけですが、そのプレッシャーを受けながら走り続けるのはなかなか大変です。
また、最後の直線が長いコースだと、差しや追い込みといった余力を残している馬に差し切られやすいのもデメリットといえるでしょう。
先行のメリット・デメリット
先行のメリットは、展開に左右されずにレースを進めやすいことです。
逃げや追い込みといった極端な脚質の馬は、レース展開によっては力を発揮しにくいことがありますが、先行はコンスタントに自分の力を発揮しやすい脚質です。
また、ゴールするまでに交わすべき馬の数が相対的に少ないので、ロスを抑えたレースができるのも先行のメリットといえます。
その一方で、逃げ馬と同様にほかの馬のターゲットになりやすいのは、先行馬のデメリットといえるでしょう。
また、比較的不利を受けにくくロスを抑えやすい脚質ではありますが、同脚質の多いレースではその限りではありません。
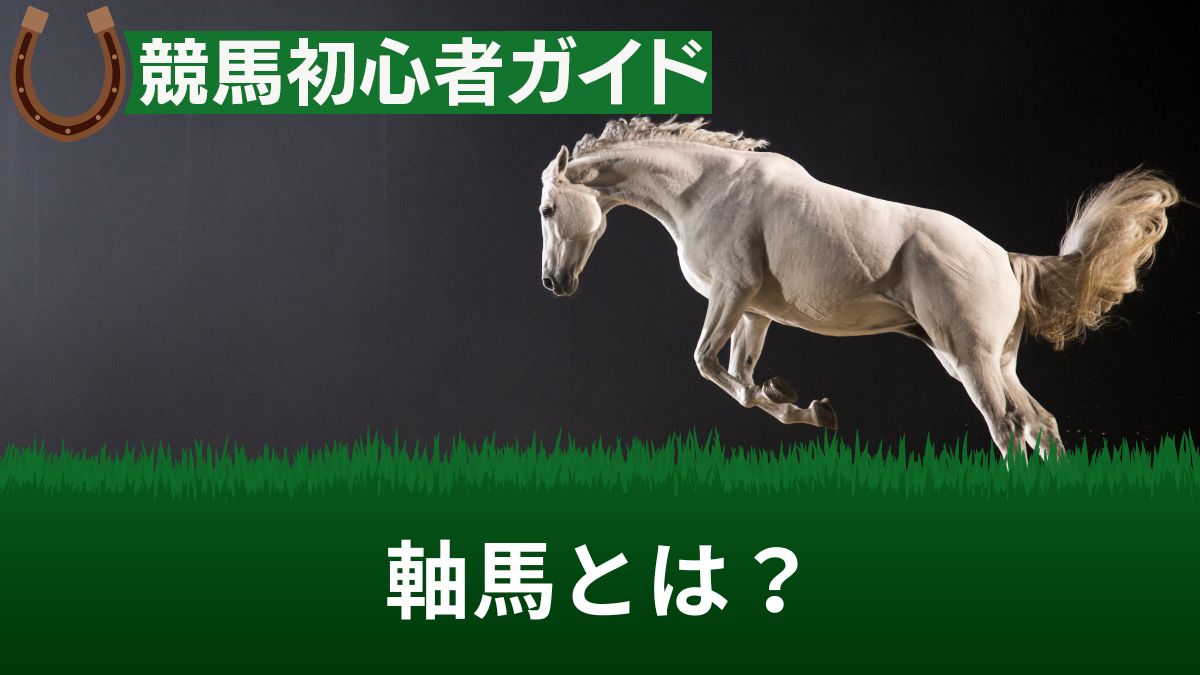
差しのメリット・デメリット
差しのメリットは、全体的に前がかりになるレースに強いことです。
現代競馬では前のほうのポジションを取ることが有利とされていますが、多くの馬が前のポジションを取ろうとすると、自然とペースは速くなります。
すると、多くの馬がゴール前でスタミナを使い果たしてしまうため、序盤に脚を温存していた差し馬に有利な展開になります。
一方、差し馬は最後の直線が短いコースでは相対的に不利な脚質です。
末脚を爆発させて前を追い抜いていこうにも、直線が短ければ不完全燃焼で終わってしまう可能性が高いでしょう。
追い込みのメリット・デメリット
追い込み馬のメリットは、最終直線が長いコースではごぼう抜きが決まりやすいことです。
前半は力を温存している分、最後の直線で最後方から一頭、また一頭と追い抜いていけるのは追い込み場の醍醐味です。
また、馬群から離れて追走するため、レース中に不利を受けにくいのも追い込み馬のメリットといえるでしょう。
追い込み馬のデメリットとしては、ペースが遅いと前をとらえきれない可能性が高いことが挙げられます。
ペースが遅いとほかの馬も余力をもって最終直線を迎えられるので、どれだけ追っても前との差が縮まらないことがあります。
また、差し馬同様に最後の直線が短いコースでは、相対的に不利な脚質といわざるをえません。
まくりのメリット・デメリット
まくりのメリットは、レースのリズムを強引に自分のリズムにできることです。
まくりという脚質はレース途中から動いていって先頭に並びかけるような脚質ですが、それまでは逃げ馬のものだったリズムを自分のリズムに置き換えることができます。
こうすることで、逃げ馬はリズムを崩して沈んでいきますし、自分は走りやすいリズムでレースを進められるでしょう。
一方、デメリットとしては、レース展開によってはまくりが不発に終わる場合があることが挙げられます。
途中で動いていっても先団にとりつくことができなかった場合、まくり馬はただスタミナを無駄に消費しただけに終わり、その後もチャンスがないまま沈んでいってしまう可能性が高いです。
競馬の脚質をアプリや新聞で把握しよう

競馬の脚質とは、「競走馬が得意とする走り方」のことで、「逃げ」「先行」「差し」「追い込み」「まくり」の5つに大きく分類されます。
レースに出走する馬がどの脚質でレースを進めるかは、競馬新聞やJRAのサイトなどで確認できる馬柱を見ることで、おおよそ想像することが可能です。
レースが行われる距離やコースによって有利な脚質・不利な脚質も変わってくるので、脚質は予想に大きな影響を与えるファクターのひとつといえます。
出走馬それぞれの脚質に着目して馬券を購入したり応援したりすることで、競馬がより楽しいものになるでしょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/