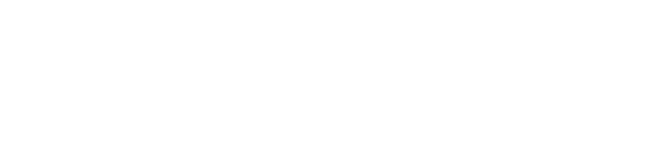競馬を始めたばかりのビギナーの方にとって、競馬の専門用語は意味がわからないものも多々あると思います。
「斤量」もそのような用語のひとつであり、意味どころか読み方もわからない方もいるでしょう。
競馬を楽しむためには、こういった専門用語をきちんと理解することが大事です。
本記事では、競馬の「斤量」について解説します。
併せて、斤量の決め方や斤量がレースに与える影響なども解説するので、競馬を始めたばかりの初心者の方はぜひ参考にしてください。
競馬の斤量とは?
競馬の斤量は、レースの予想をしたりレース観戦を楽しんだりする際に大事な要素のひとつです。
競馬の斤量について、詳しく解説します。
斤量の意味
競馬の斤量とは、競走馬がレースで背負う「負担重量」のことです。
競走馬はレースで走る際、背中にジョッキーやジョッキーが座るための鞍を乗せますが、それらの重さを総合したものが負担重量です。
たとえば「斤量57kg」という表記があった場合、その馬は自分の背中に57Kgの重量を乗せて走ることを意味します。
「斤量57kg」の場合、競走馬が背負う重量は57kgより重くとも57kgより軽くともいけません。
JRAでは、レースごとに定められた斤量になっているかを確認するために、JRA職員の立ち合いのもとで騎手が検量室で計量を行っています。

読み方は「きんりょう」
「斤量」と漢字で書かれても読み方がイマイチわからない方もいるかもしれませんが、「斤量」は「きんりょう」と読みます。
食パンを数えるときに「1斤(きん)、2斤(きん)」といった数え方をするため、そのことを知っていると読みやすいでしょう。
斤量の最大値
斤量の決め方はレースによって異なり(後述します)、中には斤量に上限がないようなルールも存在します。
そのため、理論上は斤量の最大値を決めることはできませんが、斤量が重くなりすぎるとレースで不利になりますし、馬への負担も大きくなります。
そのため、あまりに重い斤量が課されるような場合は、そのレースへの出走自体を見送るケースが大半です。
最近ではレース出走時の斤量は50kg台中盤~後半が平均ですが、過去には1951年に83kgの斤量を背負って出走した馬もいます。
ただし、その記録をもつ馬は現在のJRAで走っている馬(サラブレッド)と種類が異なるので、比較対象としては不適切かもしれません。
サラブレッドが背負った酷な斤量としては、テンポイントという馬が背負った66.5kgが有名な例として挙げられます。
テンポイントは現在からみれば「とても酷」とも思える斤量を背負って出走したレースで骨折し、長い闘病生活を経て安楽死の処分が取られました。
「稀代の名馬」とも呼ばれたテンポイントが安楽死処分になってしまったことを経て、斤量に関する議論が巻き起こり、現在では極端に重い斤量を設定しないような不文律があります。
斤量が足りない場合はどこに重りを付ける?
負担重量の大半はジョッキーの体重が占めますが、ジョッキーによって体重は若干異なるため、ジョッキーと鞍などの重量だけでは負担重量に届かないことがあるのも事実です。
その場合は、鉛の重りを足して斤量を微調整します。
鉛の重りはジョッキーが着ているベストのポケット部分に入れられるので、我々のようなレース観戦者からは重りを確認することはできません。


\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/
競馬のレースごとの斤量の決め方・ルール

斤量の決め方やルールはレースによって異なります。
それぞれの決め方・ルールの概要を、詳しく解説しましょう。
馬齢重量
馬齢重量は、2歳限定戦と3歳限定戦のみの決め方で、馬の年齢によって以下のように重さを定めます。
| 2歳戦 (9月まで) | 2歳戦 (10月~12月) | 3歳戦 | |
| 牡馬およびセン馬 | 55kg | 56kg | 57kg |
| 牝馬 | 55kg | 55kg | 55kg |
同じ2歳戦でも、レースの時期によって重さに変化があるのが特徴です。
牡馬Aと牝馬Bが8月の2歳戦で勝負した場合、どちらも斤量55kgでの勝負になります。
ただし、同じ馬が年末12月に再び相まみえた場合、牡馬Aの斤量は56kgに増えますが、牝馬Bの斤量は55kgのままです。
そのため、8月の2歳戦では牡馬Aが牝馬Bに先着していたとしても、12月には斤量の優位性を活かして牝馬Bが先着するかもしれません。
別定
「別定」と呼ばれるルールでは、レースごとに負担重量を決定する基準が設けられています。
基本重量に、収得賞金や勝利度数などを踏まえて負担重量が増減されます。
たとえば、「収得賞金1,200万円ごとに負担重量1kg増」「G2レース1着馬は1kg増」といった具合です。
また、別定レースでは異なる年齢の馬での勝負になることも多々あり、その際の負担重量の基準は「5歳以上の牡馬・せん馬が58kg(平地競走の場合)」です。
3歳や4歳の馬は、レースの距離や年齢に応じて負担重量の減量を受けることができます。
それぞれの条件は細かいのでここでは割愛しますが、たとえば「6月に開催される1,400m以上1,600m以下のオープンクラスのレース」では、3歳馬は負担重量マイナス4kgの恩恵を受けることが可能です。
この条件では、4歳以上の馬は斤量58kgなのに対して、3歳馬は58-4=54kgの重さで勝負することができます(簡単のため収得賞金の条件は省いて考えています)。
さらに、牝馬は牡馬やセン馬よりもマイナス2kgの重さになるので、同じレースに3歳牝馬が出走する際の斤量は54-2=52kgです。
4歳以上の牡馬・セン馬と比べると、58kg-52kg=6kgも軽い重さで勝負できることになります。
成長度合いの違いによる能力の違いを踏まえて重さを調整している、というイメージで考えるとよいでしょう。
定量
「定量」は先ほど説明した「別定」のルールのひとつであり、収得賞金や勝利度数などを加味せず、馬の年齢と性別だけで一定の負担重量を定める方法です。
3歳以上のG1レースはすべて「定量」で開催されており、たとえば牡馬クラシックの一冠目である「皐月賞」の負担重量はこれまでの成績に関係なく、牡馬57kg、牝馬55kgと定められています。
また、複数の世代の馬で勝負をするG1レースについても例を挙げておくと、「ジャパンカップ」の負担重量は3歳56 kg・4歳以上58 kg(牝馬は2kg減)です。
ハンデキャップ
「ハンデキャップ」は、各々の馬の能力やここ数戦の調子などを考慮して、JRAのハンデキャップ作成委員が各々の負担重量を決定するルールです。
ハンデキャップのレースでは、「出走馬全頭が同時にゴールできる設定」が目指されています。
そのため、能力のある馬やここ数戦で調子のよい馬の斤量は重めに、能力が足りない馬やここ数戦の調子が振るわない馬の斤量は軽めになる傾向があります。
重さ設定の独自性ゆえに、「荒れることが多い」といわれるのが特徴です。

【斤量の見方】競馬レースに与える影響

斤量は馬券検討をするうえで大事な要素のひとつですが、重さが異なることでどのような点に違いが生じるでしょうか。
斤量が競馬のレースに与える影響を、詳しく解説します。
スタートダッシュ
斤量が関与する大きなポイントのひとつとして、ゲートが開いた際のスタートダッシュが挙げられます。
自分が重りを背負って走ることを想像してみるとわかりやすいと思いますが、1kgの重りもつ場合よりも5kgの重りをもつほうが出脚は鈍るでしょう。
とくに先行馬の場合、スタートをしっかり決めて前目のポジションを取れるかどうかは、好走確率に大きく関わります。
これまでよりも重さが重くなってスタートダッシュがつかなそうな先行馬は、馬券検討時には軽視してもよいかもしれません。
上がり3ハロンのタイム
上がり3ハロンのタイムとは、「最後の600mを走破するタイム」のことです。
競馬の勝負では、道中は脚を温存して最後の直線で末脚を爆発させる戦法を取る馬も多いです。
そのような馬は、最後の直線で前目の馬を捕まえなければならないため、逃げや先行の馬よりも上がり3ハロンのタイムが速い傾向にあります。
ただし、スタートダッシュと同じように、重さが重くなるほど最後の直線の走破タイムが遅くなりやすいことは、想像に難くないでしょう。
上がり3ハロンタイム上位の馬が、これまでよりも重い斤量で出走する際、末脚が不発になる可能性も十分あります。
また、「上がり3ハロンのタイムが速い馬=最後の直線で他馬をごぼう抜きにしている馬」であり、そういった馬は人気になりやすいです。
斤量に着目することで、人気を吸ったうえで飛ぶ可能性が高い馬を見つけやすくなるので、美味しい馬券を取れるかもしれません。
レースタイム
斤量がスタートダッシュに関わり、上がり3ハロンのタイムにも関わってくるのであれば、当然レース全体のタイムにも重さが関与することになるでしょう。
人間にもさまざまな個性や特徴があるように、馬の個性や特徴もそれぞれの馬で異なります。
瞬発力が求められる勝負にめっぽう強い馬もいれば、他の馬がバテてしまうような消耗戦で持ち前のスタミナを活かして活躍する馬もいます。
馬券においてどちらを重視するかは、展開やタイムがどのようなものになるかによって変わってくるでしょう。
これまで軽さを活かして前半から飛ばすような形で走っていた馬が、ルールの変化によって一気に重い斤量を背負わされた際、これまでのような走りができない可能性もあります。
そうすると、ペースが落ち着いてスタミナが温存されやすくなるので、最後の末脚勝負になりやすいです。
展開の推測はタイムを推測することにもつながりますが、その根幹となる考え方に斤量は大きく関与します。
騎手の体重管理
冒頭でも少し触れましたが、斤量の大半は馬にまたがる騎手の体重が占めます。
騎手の体重と鞍の合計が斤量に満たない際は、重りを使うことで調整できますが、逆に騎手の体重と鞍の合計が斤量オーバーの際は調整できません。
そのため、競馬の騎手は常に厳しい体重管理を行っています。
例えば、ある騎手が週末に5回騎乗し、それぞれの斤量の条件が「57kg」「58kg」「55kg」「55kg」「53kg」だったとしましょう。
足りない分に関しては重りで補えばよいので、騎手としては今回の中でもっとも軽い「53kg」の重さを超えないように体重管理をしなければなりません。
競馬の鞍の重さは3kg程度だそうなので、53-3=50kgを超えないように調整することが求められます。
ハンデキャップ戦で少し能力が足りないと思われる馬の場合、斤量が50kgを切ることも稀にあります。
そのような馬に騎乗する騎手は、体重管理をかなりシビアに意識しなければなりません。

馬の故障しやすさ
記事前半でテンポイントについて少し触れましたが、斤量は競走馬にとっては負担でしかありません。
そのため、重くなればなるほど馬は厳しい負荷の中で走らなければならないので、故障を発生しやすくなります。
「この勝負でどのようなパフォーマンスを見せてくれるか」が大事であり、その後のことは特に興味がない方もいるかもしれません。
ただ、後日馬に故障が発生したという話を耳にするのは、決して心地のよいものではないはずです。
サラブレッドが故障なく走り続けられるような斤量設定を心がけてもらうことで、我々競馬ファンも安心して応援しやすくなるでしょう。
斤量の決め方や競馬のレースに与える影響を把握しよう

斤量は競走馬がレースを走る際に負担する重量であり、騎手の体重や騎手が座るための鞍の重さを合計したものです。
斤量の決め方はレースのルールによって異なり、一律同じような重さで勝負するレースもあれば、各々の馬の能力やここ数戦の調子などを考慮して重さが決められるレースもあります。
斤量は馬のスタートダッシュや最後の直線での末脚の爆発力などに関わるので、馬券検討をするうえで重視するべきポイントのひとつです。
とくに体重が軽く小柄な馬にとって、斤量による作用は無視できません。
人間でも、体重が重い方よりも体重の軽い方のほうが、抱える荷物の重さの変化に対してより敏感なはずです。
そういったところを踏まえて馬券検討をして的中させられるととても気持ちよいので、馬券を購入する際はぜひ斤量に着目してみましょう。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/