
レースで走る競走馬は、「斤量」と呼ばれる負担重量を背負うことがルールで決められています。
斤量の決め方にはいくつかのパターンがありますが、そのうちのひとつが「ハンデキャップ」と呼ばれる方法です。
「ハンデキャップ」のルールでは、どのような形で重さが決められるのでしょうか。
本記事では、「ハンデキャップ」と呼ばれる斤量の決め方の概要を解説します。
あわせて、ハンデ戦が荒れやすい理由やハンデ戦での馬券戦略なども解説するので、馬券のプラス収支を目指している方はぜひ参考にしてください。
競馬のハンデキャップとは?

競馬ではレースごとに決められたルールにもとづいて、競走馬が勝負中に背負う重さ(=負担重量)を決めます。
斤量の決め方にはいくつかのルールがありますが、そのうちのひとつが「ハンデキャップ」と呼ばれる決め方です。
ハンデキャップのレースでは、出走馬の能力やここ数戦の調子などを考慮して、JRAのハンデキャップ作成委員が各出走馬の斤量を決定します。
ハンデキャップのルールで行われる勝負のことを一般的に「ハンデ戦」と呼びますが、ハンデ戦では「出走馬全頭が同時にゴール可能な重さ設定」が目標とされています。
そのため、近走で調子のよい馬や実力が上だと考えられている馬には、重めの斤量が課されるのが一般的です。
一方、近走があまり振るわない馬や力が少し足りない可能性がある馬には、軽めの斤量が設定されます。

重賞のハンデ戦一覧
JRAでは、さまざまな条件でハンデ戦が行われています。
馬券を購入するにあたって、ハンデ戦かどうかは大事なポイントになり得るので、JRAが実施しているハンデ戦の中で「重賞」と呼ばれるものを、以下に表でまとめました。
なお、重賞はG1、G2、G3に分類され、数字が小さくなるほど格が高くなりますが、もっとも格の高いG1にハンデ戦はありません。
| 時期 | 芝 | ダート |
| 1月 | G3中山金杯(2,000m) G3京都金杯(1,600m) G2日経新春杯(2,200m) G3小倉牝馬ステークス(2,000m) | – |
| 2月 | G3シルクロードステークス(1,200m) G3ダイヤモンドステークス(3,400m) G3小倉大賞典(1,800m) | – |
| 3月 | G3中山牝馬ステークス(1,800m) | G3マーチステークス (1,800m) |
| 4月 | G3ダービー卿チャレンジトロフィー(1,600m) | – |
| 5月 | G3新潟大賞典(2,000m) G2目黒記念(2,500m) | – |
| 6月 | G3府中牝馬ステークス(1,800m) G3ラジオNIKKEI賞(1,800m) G3函館記念(2,000m) | – |
| 7月 | G3北九州記念(1,200m) G3七夕賞(2,000m) G3小倉記念(2,000m) G3関屋記念(1,600m) | – |
| 8月 | G3CBC賞(1,200m) | – |
| 9月 | G3京成杯オータムハンデ(1,600m) G3チャレンジカップ(2,000m) | G3シリウスステークス (2,000m) |
| 10月 | – | – |
| 11月 | G2アルゼンチン共和国杯(2,500m) G3福島記念(2,000m) | – |
| 12月 | G3中日新聞杯(2,000n) G3ターコイズステークス(1,600m) | – |
ハンデ戦の重賞は計27つあり、そのうち大半は芝の重賞です。
ダートのハンデ重賞は、3月のマーチステークスと9月のシリウスステークスの2つだけです。
また、芝の重賞のうちG2は日経新春杯、目黒記念、アルゼンチン共和国杯の3つだけなので、ハンデ戦の大半は芝のG3重賞ということになります。
後述しますが、ハンデ戦にはハンデ戦なりの馬券のポイントがあるので、重賞を中心に馬券を仕込む場合は、どの重賞がハンデ戦かを把握しておく必要があります。

競馬でのハンデキャップ以外の斤量の決め方

競馬での斤量の決め方は、ハンデキャップだけではありません。
ハンデキャップ以外の斤量の決め方を、以下で紹介しましょう。
馬齢重量
馬齢重量は、2歳限定戦と3歳限定戦のみの斤量の決め方で、馬の年齢によって以下のように重さを定めます。
| 2歳戦(9月まで) | 2歳戦(10~12月) | 3歳戦 | |
| 牡馬およびセン馬 | 55kg | 56kg | 57kg |
| 牝馬 | 55kg | 55kg | 55kg |
成長するにつれて、牡馬・セン馬と牝馬で重さに差が生じていくのが大きな特徴です。
別定
「別定」と呼ばれるルールでは、レースごとに負担重量を決定する基準が設けられており、基本重量に収得賞金や勝利度数などを踏まえて負担重量が増減されます。
たとえば、「収得賞金1,200万円ごとに負担重量1kg増」「G1の1着馬は2kg増」といった具合です。
また、別定レースには異なる年齢の馬が出走するケースも多々あり、その際の負担重量の基準は「5歳以上の牡馬・せん馬が58kg(平地競走の場合)」です。
3歳や4歳の馬は、レースの距離や年齢に応じて負担重量の減量を受けることができます。
それぞれの条件は細かいのでここでは割愛しますが、たとえば「8月に開催される1,600m超2,200m未満のオープンクラスのレース」では、3歳馬は負担重量マイナス3kgの恩恵を受けることが可能です。
成長度合いの違いによる能力の違いを踏まえて重さを調整している、というイメージで考えるとよいでしょう。
定量
「定量」は先ほど説明した「別定」のルールのひとつであり、収得賞金や勝利度数などを加味せず、馬の年齢と性別だけで一定の負担重量を定める方法です。
3歳以上のG1はすべて「定量」で開催されており、たとえば牡馬クラシックの三冠目である「菊花賞」の負担重量は出走過程の成績に関係なく、牡馬57kg、牝馬55kgと定められています。
また、複数の世代の馬で勝負をするG1についても例を挙げておくと、「天皇賞秋」の負担重量は3歳56 kg・4歳以上58 kg(牝馬は2kg減)です。
ハンデ戦が荒れることが多い理由
ハンデ戦は馬齢重量や定量での勝負と比べると荒れといわれることが多く、実際に何度も高配当を生み出してきています。
ハンデ戦が荒れることが多い理由を、以下で解説しましょう。
人気薄が好走しやすい下地が整えられているため
実力差のある馬同士が勝負をすると、実力がより優れている馬が楽勝するのが普通です。
しかしハンデ戦では、「出走全馬が横一線でゴール可能な重さ設定」という前提のもとで、各馬の能力を踏まえた斤量設定が行われます。
そのため、ガチンコ勝負だと分が悪い馬でも、軽ハンデの有利な条件で勝負が可能なことで、実力が上の馬といい勝負ができるようになっています。
実力が上の馬がスタートに失敗したり展開面で不利だったりすると、軽ハンデの馬がより激走しやすくなるので、結果として荒れる決着になりやすいのでしょう。
ハンデキャップ設定が適切でない可能性があるため
ハンデ戦では、JRAのハンデキャップ作成委員が各馬の斤量を設定します。
重さの設定に際しては、各馬の成績や近走の様子などを細かく確認しますし、ハンデキャップ作成委員はその道のプロでもあります。
とはいえ、ハンデキャップ作成委員はコンピューターではなく人間なので、毎回斤量を完璧に設定できるわけではありません。
実力が1枚上の馬の斤量を、本来あるべき重さより軽めに据え置いてしまったり、力が少し足りない馬に重めの斤量を設定したりしてしまう可能性もあるでしょう。
その結果、本来もっと人気をしてもよい馬が不当な人気に落ち着き、その馬が激走して荒れた決着を演出する可能性も考えられます。
逆にいえば、「この馬もっと斤量背負っても悪くないと思うんだけどな」「この馬にこの斤量は重すぎだろ」と思えるような馬がいるハンデ戦は、美味しい馬券を的中させるチャンスかもしれません。
ハンデ戦の馬券で勝つためのポイント
ハンデ戦が荒れやすいレースなのであれば、ハンデ戦で馬券を的中させれば自ずと高配当を得やすくなるでしょう。
ハンデ戦の馬券で勝つためのポイントを、以下で紹介します。
出走馬の得意条件・不得意条件をチェックする
どのような条件でも好走できるオールラウンダーでない限り、競走馬にはそれぞれ得意条件や不得意条件があります。
右回りの中距離なら無難にこなす馬もいれば、東京コースのマイルでなければからっきしの馬もいるでしょう。
出走馬の得意条件・不得意条件をチェックして、その条件に当てはまっている馬の評価を上げる(もしくは下げる)のは、ハンデ戦でなくても大事なポイントです。
とくに、人気になるであろう馬の得意条件や不得意条件はしっかりチェックする必要があります。
得意条件に当てはまっているのであれば馬券は堅く決まりそうですが、不得意条件に当てはまっていれば波乱が期待できるかもしれません。
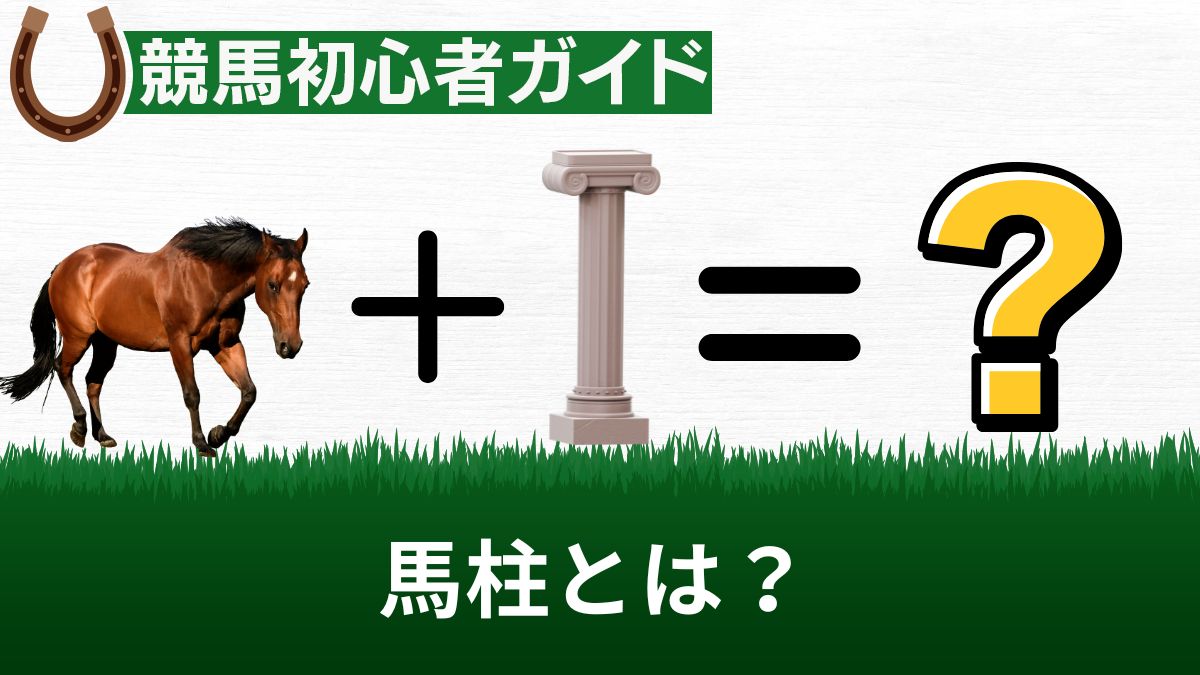
末脚勝負の馬の斤量は要チェック
競走馬の脚質はそれぞれ異なり、「差し」や「追い込み」と呼ばれる馬は、最後の直線での爆発的な末脚で勝負することが多いです。
差しや追い込みなどの末脚勝負の馬が背負っている斤量がどれくらいかは、予想に大きな影響を与えます。
自分に置き換えてもらうとわかりやすいと思うのですが、荷物を背負ってランニングをすることを考えてみてください。
このとき、重い荷物と軽い荷物、どちらを背負った状態のほうが最後のダッシュがしんどいかといわれれば、当然重い荷物のほうでしょう。
馬も同じで、斤量が重くなればなるほど末脚が鈍る可能性が高いです。
末脚勝負でほかの馬をなぎ倒してきた馬が、ハンデ戦でこれまでよりも重めの斤量を背負うことで、今までのような末脚を出せずに惨敗してきたケースはいくつもあります。
人気どころの馬は後方待機することが多く、それらの馬の負担重量が軒並み重めに設定されているようなレースは、波乱の匂いがプンプンします。

最重量ハンデの馬は比較的信頼できる
ハンデ戦の基本的な考え方は、「負担重量が重い馬=ハンデキャップ作成委員に力を認められている馬」です。
つまり、最重量ハンデの馬は、「今回出走する馬の中でもっとも実力がある馬」と考えることができます。
もちろん、ハンデキャップ作成委員が馬の力を見誤った可能性は否定できませんが、ハンデキャップ作成委員は馬の力を見抜くプロです。
そのため、最重量ハンデの馬は馬券を的中させるという観点で考えたときに、比較的信頼できる馬といってもよいでしょう。
ハンデ戦と聞くと、ついついハンデが軽めの馬を買いたくなってしまう方もいるかもしれません。
しかし、ハンデ戦での斤量設定の仕組みを知っていれば、信頼して購入できるのはむしろハンデが重いほうの馬であることがわかるはずです。
軽ハンデの馬はヒモまでの評価にとどめるのが無難
ハンデが重い馬が「もっとも力がある馬」なのであれば、ハンデが軽い馬は「力の面では一歩劣る可能性が高い馬」といえます。
「斤量が軽いハンデをもらってようやく他の馬といい勝負ができる」と、ハンデキャップ作成委員に考えられていることを意味するからです。
そういった馬はスタートをきれいに出て、展開が向いて、最後の直線もスムーズに走れて、ようやく好勝負できます。
逆にいえば、少しでもその馬に対して不利な要素があれば、馬券圏内には届かない可能性が高いので、馬券に組み込むにしても軸ではなくヒモまでの評価にとどめるのが無難です。
とはいえ、自分の判断からすると「その馬にそのハンデは軽すぎじゃない?」というようなハンデ設定の馬が、出走することもあります。
そういったときは自分の感覚を信じて、軽ハンデの馬を馬券の中心に据えるのもひとつの方法です。
競馬のハンデキャップは斤量の決め方のひとつ

競馬で出走馬が背負う斤量の決め方はいくつかあり、「ハンデキャップ」はそのような決め方のひとつです。
出走馬の能力やここ数戦の調子などを考慮して、JRAのハンデキャップ作成委員が各出走馬の斤量を決定します。
馬齢重量や別定などと異なり、「JRAのハンデキャップ作成委員による判断」で斤量が決められるという特殊性から、ハンデ戦は荒れることも多いです。
他の馬よりも重めの斤量を設定されている馬に隙はないか、他の馬よりも軽めの斤量を設定されている馬の強みを活かせる条件ではないかなどを探ることで、美味しい馬券を的中できるかもしれません。
斤量設定の方法を踏まえたうえで馬券の組み立て方を意識できるようになれば、競馬沼にまた一歩足を踏み入れたことになるかもしれませんね。










