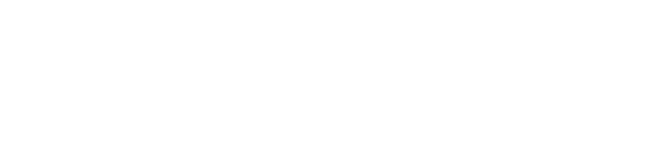競馬のレースでは、最大で18頭もの馬が合図と同時に一斉にゲートを出て、一団となって走ります。
それだけ数が多いと馬群の前のほうを走る馬もいれば、後ろのほうになる馬もいるでしょう。
競馬ではレース道中のポジションに応じた「脚質」というものがありますが、その脚質のひとつに「先行」と呼ばれるものがあります。
本記事では、「先行」とはどのような脚質なのかを解説します。
併せて、先行馬のメリット・デメリットや競馬で先行馬を買うべきケースなども解説するので、ぜひ参考にしてください。
競馬の「先行」とは?
競馬の先行とは、馬群の前のほうでレースを進める脚質の馬を指します。
「先行」という漢字を「先に行く」と読めば、イメージしやすいでしょう。
「馬群の前のほう」というのはやや曖昧な表現ですが、実際のところ「どれくらい前なら先行か」に関して具体的な定義があるわけではありません。
先頭でレースを引っ張る馬は「逃げ」という脚質に分類されるので、「先行」ではありません(逃げについて詳しくは後述します)。
そのため、「馬群の前のほう5%~45%あたり」を駆けている馬を、おおまかに「先行」というくくりにするのが一般的です。
18頭立てのレースであれば、「前から数えて1ケタ番目あたりを走っている馬までが先行」という認識でおおよそ問題ありません。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/
競馬の「先行」以外の脚質

競馬には「先行」以外に、先ほども少し触れた「逃げ」を含めていくつかの脚質があります。
人によって分類が異なる場合もありますが、「先行」以外の基本的な脚質を以下で解説しましょう。
逃げ
「逃げ」は名前のイメージどおり、レースにおいて先頭を走る脚質を指します。
逃げの馬が1頭しかいなければ単独での逃げになりますが、逃げの馬が2頭以上いる場合、レースがどのような形で進むかは始まってみなければわかりません。
逃げの馬同士で競り合いながら進むケースもありますし、1頭が抜きんでて逃げてほかの逃げの馬が結果的に「先行」のポジションに落ち着いてレースをすることになる場合もあります。
一般的にレースのペースは、逃げ馬がどれくらいのペースで逃げるかによるため、レースの流れを左右する脚質です。
サイレンススズカやパンサラッサのように印象に残るレースをする馬も多く、ファンが多い脚質ともいえるでしょう。
差し
「差し」は、レースにおいて馬群の後ろのほうを走る脚質を指します。
先行馬の後ろを走るのが差しの馬になりますが、馬群をちょうど半分に割って前半分が先行、後ろ半分が差し、というように区別するわけではありません。
先行と差しの分布はグラデーションのようになっており、馬群でのポジションが前から後ろになるにつれて、徐々に選考から差しに傾いていくようなイメージです。
差しの馬は、最終直線に向かう頃にはまだ馬群の後方にいることが多く、最後の爆発的な末脚で勝負をする馬が多くなります。

追い込み
「追い込み」は、レースにおいて「差し」の馬よりもさらに後ろ、馬群の最後方を走る脚質を指します。
仮に18頭でレースを走るとすると、後方にいる3~4頭程度の馬が「追い込み」という脚質に該当することになるでしょう。
どのようなレースでも必ず後ろに陣取る戦法を取る馬もいれば、スタートで出遅れて意に反して追い込みになるような馬もいます。
差しの馬より後方にいることから、ほぼすべての力を最終直線まで温存して、最終直線でごぼう抜きするようなレースが特徴です。

競馬のレースでの通過順による先行馬の調べ方
競馬のレースでどの馬が先行脚質でレースを進めるかは、実際にレースがスタートするまでわかりません。
普段は前のほうにいる馬でも、スタートに失敗して後方からのレースになってしまうようなケースもあるからです。
しかし、どの馬が前に行きそうかに関しては、競馬新聞などの馬柱を見ることである程度想像することができます。
たとえば、2025年の東京優駿(ダービー)を制したクロワデュノールという馬の、ダービー出走時の馬柱は以下のとおりです。
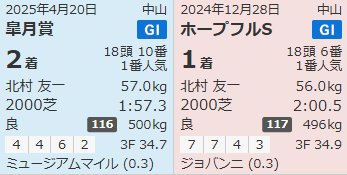
クロワデュノールは前走の皐月賞でのコーナー通過順が「(前から)4番手→4番手→6番手→2番手」、前々走のホープフルSでのコーナー通過順が「7番手→7番手→4番手→3番手」になっていることがわかります。
どちらのレースも18頭立てのレースなので、クロワデュノールは前走も前々走も「先行」脚質でレースを進めていることになります。
そのため、ダービーにおいても先行でレースを進める可能性が高いと判断できるでしょう。
馬柱は競馬新聞やJRAのサイトなどで確認できるので、レースにおいてどの馬が先行しそうかを判断するための材料として、確認するのがおすすめです。
競馬のレースにおける先行馬のメリット

競走馬はさまざまな脚質でレースを走りますが、それぞれの脚質は特徴やメリット・デメリットがそれぞれ異なります。
ここでは、競馬のレースにおける先行馬のメリットを見ていきましょう。
レース展開に左右されずに走りやすい
先行の馬は、馬群全体から見ればバランスのよいところでレースを進められます。
そのため、レース展開に左右されずに走りやすいのが特徴です。
逃げの馬は、ほかに逃げの馬が何頭もいると自分のリズムで走ることができずに、力を発揮できない可能性があります。
追い込みの馬は、逃げ馬がペースを上げずに大半の馬が脚を温存したままで最終直線に向かってしまえば、前の馬をごぼう抜きするのは困難です。
自分のパフォーマンスをある程度安定して発揮しやすいのは、先行馬の大きな魅力のひとつといえるでしょう。
不利を受けにくい
競馬のレースでは十数頭の馬が同時に走るので、道中の位置取り次第ではほかの馬が邪魔になって不利を受ける可能性があります。
不利を受けやすいのは馬群の後方にいる馬であり、馬群の前方で走る先行脚質の馬は不利を受けにくいこともメリットのひとつです。
不利を受けてしまえば実力を出し切れないまま負けてしまう可能性もあるので、この点においても先行馬はパフォーマンスを発揮しやすいといえるでしょう。

コースロスを減らせる
差しや追い込みの馬が前の馬をかわす場合、前を走っている馬を避けて大きく外を回るような進路取りになるのが一般的です。
ただし、そのような形でレースを進めると、コースの内をぴったり回ってくる馬よりもロスの大きな走りになってしまいます。
先行馬はかわすべき馬の数が多くないので、コースロスを最小限に抑えながらレースを進めることが可能です。
とくに実力に差のない馬同士が走る場合、コースロスをどれだけ抑えられるかは、最終的な着順に大きく影響します。
競馬のレースにおける先行馬のデメリット
「先行」という脚質でレースを進めることには、上述したようにいくつもメリットがありますが、もちろんデメリットがないわけではありません。
競馬のレースにおける先行馬のデメリットについて、解説しましょう。
目標にされやすい
競馬のレースでは、1着を取ることを目標としてすべての馬が走ります。
1着を取るためには「なるべく速く走ること」が大事なことはいうまでもありませんが、より本質的には「出走馬のなかでもっとも速く走ること」が求められます。
先行馬はよいポジションを取りやすいですが、それは「後ろの馬からの目標になりやすい」ということでもあるのです。
後ろの馬は先に抜け出した馬を捕まえられるように走ればいいわけですから、とてもレースを進めやすいです。
とくに後方の馬に有力な馬がいると、先行馬は格好の目標になることを念頭に置いて、レースの予想をしなければなりません。
同脚質が多いと競り合いになりやすい
レースによって脚質分布はバラバラですが、出走メンバーによっては特定の脚質に偏るような場合もあります。
先行馬は基本的に馬群の前のほうでレースを進めますが、同じようなことを考えている馬がほかにもたくさんいると、当然馬群の前のほうはごった返します。
その結果、自分に有利なポジションを取るために競り合いになって、スタミナを無駄にロスしてしまうことも予想されるでしょう。
レース中にスタミナをロスしてしまうと、最後に踏ん張るだけの力は当然残されていません。
その結果、後方の馬たちになすがままにされるような展開になってしまう可能性もあります。

競馬で先行馬を買うべきケース
馬場の造成技術が向上しておりタイムが出やすい現代競馬では、一般的に先行馬は有利にレースを運びやすいとされています。
そのなかでも、とくに先行馬を買うべきいくつかのケースを紹介しましょう。
小回りの競馬場でのレース
競馬の脚質を、「逃げ・先行」の前方脚質と「差し・追い込み」の後方脚質に大きく分類した場合、後方脚質は最後の直線が長いコースのほうが実力を発揮しやすいです。
そのため、裏を返せば小回りで最後の直線があまり長いコースでは、後方脚質よりも前方脚質の馬のほうが相対的に有利に走れます。
また、小回りのコースはカーブが急なことも多く、後方の馬がスピードを殺さずに加速しながらカーブを曲がるのは至難の業です。
そういった要素が相まって、小回りの競馬場では先行馬のほうが後方脚質の馬よりも成績がよい傾向にあります。
短距離レース
短距離レースはスタートしてから数十秒でゴールを迎えるため、道中のわずかな不利や進路取りのロスが着順に大きな影響を与えやすいです。
そのため、差しや追い込みといった不利を受けやすい脚質よりも、不利を受けにくい先行脚質の馬は相対的に有利なレースをしやすいといえるでしょう。
また、短距離レースのなかでもとくに距離の短い1,200mのレースでは、最終直線があまり長くないコースが大半です。
上で触れた「後方脚質の馬が実力を発揮しにくい」ことも相まって、先行馬に有利な状況が整っているといえます。
先行馬が少ないレース
先行馬のデメリットとして、「同脚質が多いと競り合いにつながりやすい」ことを先ほど挙げました。
しかしそれは、「先行馬が少なければ争いも起きにくく、有利なポジションを取りやすい」ということでもあります。
先行馬が少ないかどうかは各出走馬の馬柱を見ればある程度判断でき、出走馬のなかで先行しそうな馬が1,2頭程度しかいなさそうな場合は、大チャンスです。
先行馬が少なそうだと判断できるレースでは、多少力の面では見劣りする先行馬でも有利にレースを進めやすいので、大番狂わせを期待して先行馬を買ってみるのもよいかもしれません。
先行馬が多い場合は先行力や指数が抜けている馬
先行馬がある程度多い場合でも先行馬から馬券を購入したい場合は、先行力や指数の面で抜けている馬を中心に考えるのがよいでしょう。
先行馬には、「何が何でも先行したい馬」もいれば「流れのなかでうまく先行できれば先行する馬」もいます。
そのような馬同士が競った場合、前者の馬のほうが先行ポジションを確保しやすいのは、想像に難くありません。
また、有料で発行されている競馬新聞やnoteなどでは、それぞれの馬に「指数」が割り振られていることもあります。
指数の内容はさまざまですが、「先行指数」といった指数が用いられていることもあり、先行指数上位の馬はそのレースで自然と前に行きやすい馬だと考えられるでしょう。
先行しそうな馬がどの馬か判断しにくい場合は、そういった指数を参考にしながら想像するのもおすすめです。

競馬の先行馬はレースを有利に運べることが多い

競馬の「先行」とは、馬群の前のほうでレースを進める馬のことを指します。
逃げや追い込みといった極端な脚質とは異なり、レース展開に左右されにくいですし、進路取りのロスを抑えながら走りやすいのがメリットです。
その一方で目標にされやすいことや、先行脚質が多いと競り合いになりやすいといったデメリットがあることは、把握しておかなければなりません。
現代競馬では先行馬は有利にレースを運びやすいですが、とくに小回りコースや先行馬が少ないレースにおいては、その有利さはより顕著なものになります。
予想の段階でどの馬が先行するのかを自分なりに考えて、見事その予想が当たれば気持ちよいですし、そのうえで馬券も仕留めることができれば、いうことはありません。
それぞれの馬の脚質に注目したうえで、予想やレース観戦をしてみてはいかがでしょうか。

\パチンコ・パチスロ・競馬・スポーツ・カジノゲームなど盛りだくさん!/